| Crossover/Fusion �u���T�}�[�t���[�W��������I 2001 �@�܂�ŔM�ђn��̂悤�ȋC��̍��N�̉āB�ЂƐS�n���Ďv�l��H�������C���ɂȂ����Ƃ���ŁA�S�n�ǂ��Ă��y���ɉ߂��������ɍœK�ȃt���[�W�����E�A���o�������Љ�܂��傤�B���łɏՌ��̖\�I�b�����Љ�(^^;;)�B(2001/07/28 update) |
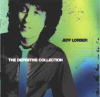 Jeff Lorber /The Definitive Collection (2000�N) �������Ȃ蔽���C���̃Z���N�V��������B�}���`�E�L�[�{�[�f�B�X�g�Ńv���f���[�T�[�Ƃ��đ劈���Jeff Loeber�B2000�N�Ƀ����[�X���ꂽARISTA����̃A���o������̃R���s���[�V�����ł��B�ނ̐Ⓒ���Ƃ����鎞��́A��������ʖ��Ղ���̃Z���N�V�����B�wWater Sign�x(79�N)�A�wWizard Island�x(80�N)�A�wGalaxian�x(81�N)�A�wIt's A Fact�x(82�N)�A�wIn The Heat of the Night�x(84�N)�A�wStep By Step�x(85�N)�B�܂�Ŗ��̂悤�ł��B �@�ނ̃T�E���h�̓����ł���y���^�b�`�̃s�A�m�E�v���C�ɗ��ރt�@���L�[�ȃ��Y���ƁA���ʂȃT�E���h�E�o���G�[�V���������\�ł��܂��B����ɐe���݂₷�������f�B�E���C���ƕ�����₷���ȍ\���Ƃ�����������������Fusion�T�E���h�̑�햡�i�ł��܂��B���b�c���̉������܂܂�Ă��邱�̃A���o���́A���߂Ĕނ̍�i���Ƃ����l�ւ̓���҂Ƃ��Ă��A�̂���̃t�@�����Ƃ肠�����̂P���Ƃ��Ă����E�߂ł��B�y�����������邯��ǎ��͒��e�N���t�r�V�o�V�Ƃ����A����̐��݂����ȍ�i�W�ł��B |
Dan Siegel/S.t (1982�N) ��L.A.�t���[�W�����̑�\�I��̂悤�ɏЉ��邱�Ƃ̑������̃A���o���ł����A���͌��\�����̃e�C�X�g���Ǝv���܂��B�o�b�N��A.Laboriel�AJ.Robinson�AP.Jackson,Jr.,�ALarry Carlton�ȂǗL���X�^�W�I�E�~���[�W�V�����炪�勓���ĎQ�����Ă�����̂́A�����ނ�̓����I�ȃv���C�͂���قǕ������Ƃ͂ł��܂���B���ꂭ�炢���C���̃}���`�E�L�[�{�[�f�B�X�g��D.Siegel�߂��y�Ă���Ƃ������Ƃł��傤�B���������ۂ��V���Z�E�T�E���h�̋Ȃ�����̂ŁA���A���^�C���ł��̃A���o�����Ă��Ȃ��l�ɂ́A�����₷�������f�B�E���C���ƂƂ��ɓ����̔����C�[�W�[����X�j���O�I�Ȉ�ۂ�^���Ă��܂��̂�������܂���B�ł�����قnjy�₩�ȃ^�b�`�̋Ȃň��Ă��܂��B �@98�N�ɂȂ�܂Ŗ��b�c���ł����B�������t�@���Ɏx������Ă������̂̂Ȃ��Ȃ��z�̖ڂ��݂邱�ƂȂ��A�����͑Җ]�̂b�c���Ƃ��Ęb��ɂȂ�܂����B�I���W�i���̃}�X�^�����O������Bernie Grundman�ŁACD�ŕ����Ă��A�i���O�ȗD�����Ɉ��Ă���̂́A���������Ċ����ł��B |
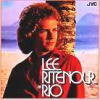 Lee Ritenour /in RIO (1979�N) ���c���̍�����u���W�����y�ɐe����ł����Ƃ���Rit�̖��������Đ��삵���S�ăK�b�g�E�M�^�[���g�p�����A���o���B�ނ̃f�r���[���̃M�u�\��335�̃Z�~�E�A�R�[�X�e�B�b�N�E�M�^�[�ɐe�������̃t�@���ɂ���A�����Ȃ�S�҃A�R�M���g�����āA��敨���ȂȂ�Ďv�������̂ł����B�Ƃ��낪���̃A���o���̓��I�A���X�A�m�x�Ƃ��ꂼ�ꌻ�n�̃~���[�W�V�����𒆐S�ɋN�p����قNjÂ�ɋÂ������e�ň����ȃC�[�W�[����X�j���O�ɂ��Ă����ɂܑ͖̖����قǏ[�����Ă��܂��B�u���W�����y�Ƃ��������̈�o���̂悤�ɕ����ԃA���g�j�I�E�J�����X�E�r�W�����Ƃ����l�B�q�������g�����Ȃ蕷������ł����炵���B���ȉƂŒm����ނł���(^^;;)�A�����u���W���l�Ƃ������Ƃ�����A�܂��ɓ����̂P�����ƌ�����ł��傤�B �@���߂��Ă���Ȃ͂�������M�^���X�g�Ƃ��Ă�Rit�̖��͂Ɉ�ꂽ�D�ꂽ��i����B�����Fusion���Ղɋ����Ă��悢�ł��傤�B�A�R�[�X�e�B�b�N�ȃM�^�[�E�T�E���h�̓u���W���A���E�e�C�X�g�̂���������̂����Ƀ��]�[�g�ȕ��͋C��Y�킹�Ă��āA���̎����̕K���i�Ƃ��Ă��E�߂ł��B |
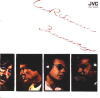 Lee Ritenour /Friendship (1978�N) ��Rit�Ռ��̃_�C���N�g�E�J�b�e�B���O�E�V���[�Y�̍ŏI�ҁB�����A�i���O�^���������݂��Ă��Ȃ���������ɁA���t�E�^���E���R�[�h���Ղւ̃J�b�b�e�B���O�܂ł̐���H������C�ɍs���Ƃ������d�ƌ�����قǂ̎�@�ŁA�ō������̉����Đ���ڎw���čs��ꂽ��i�Â���́A�����Crossover/Fusion�T�E���h�̂��G�l���M�[���������܂��BE.Watts�AD.Grusin�AA.Laboriel�AS.Forman�AS.Gadd�AD.Grusin��LA�̋��̓~���[�W�V�����B�ɂ��ꔭ�^��...���ɂْ̋����ƂƂĂ��Ȃ��_�C�i�~�Y��...����Ȋ�Ղ̏u�Ԃ��������Ă��P���Ă���悤�Ɏv���܂��BS.Forman�ɂ��N���X�^���ȃp�[�J�b�V���������Ɍ��ʓI�ŁA�A���o���S�̂ɋ����������Ɖ��s�����^�ẴE�C���h�E�x���̂悤�Ŏ��ɑu�₩�ł��B �@����ȃT�E���h�ɐe����ł������A���^�C���h���A���̃X���[�X�E�W���Y�̂悤�ȃT�E���h�ɔᔻ�I�ɂȂ��Ă��܂��̂́A���ۂɕ����Ă���������Έꔭ�ł�����������������̂Ǝv���܂��B�ӌŒn�ȃW���Y�E�t�@���ɂ͔ᔻ����Ă��A���̃X���[�X�E�W���Y�E�t�@���ɂ͕���͌��킹�܂���(^^;;)�B �@ |
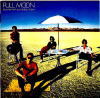 Full Moon /Featuring Neil Larsen & Buzz Feiten (1982�N) ��AOR�Ȑl�B���������Ȏx�����Ă���ނ�ł����A���ۂ�Fuion�Ȑl�B���Ǝv���܂��iNiel�{�l�Ɍ��킹���Jazz�~���[�W�V�����Ȃ����ł���...�j�B�A���o���E�W���P�b�g�Ɏʂ鏋�ꂵ�����e�̖�Y�����t�ł�T�E���h�͊��L�������ۂ��}�C���h�����ŁA�e�C�X�g�͎��ɑu�₩�B���Œp������������Buzzy�̃{�[�J���͗D�����������コ�������Ă��܂��قǑ@�ׂŁA�ނ̑t�ł�t�@�Y�ƃG�R�[�����Ղ�̃M�^�[�E�T�E���h�͓������^�b�v���B�����Niel�̓Ɠ��ȃI���K���E�T�E���h�́A����܂����s�����\���Ɋ�����������̂ŁA��������ۗ����������������Ď���̃��C���X�g���[���ɂ����Ƃ����܂��B �@�����̃h���C�r���O�E�T�E���h�̕K���i�Ƃ��ĊC���R���Ƃ����b�ɂȂ������������Ǝv���܂��B�^�Ă̗z�˂����������ގԓ��̃J�[�E�I�[�f�B�I�ŕ����ނ�̃T�E���h...�����A�ǂ����ゾ�����ȂƊ����ɐZ�鎄�������肵�܂�(^^;;)�B����ȃo���h���ē�x�Əo�Ă��Ȃ��ł��傤�ˁB |
 Willie Bobo /BOBO (1979�N) �����e���E�p�[�J�b�V�����t�҂Ƃ���60�N�ォ�犈�Ă����䏊Bobo�̃��W���[�E�f�r���[�ՁB�{�[�J���E�`���[�����������̂̑S�҂ɓ������e���̍���͂܂��ɉđS�J�̃C���[�W�B����ȏ��������ɂ����������Ƃ̂ł��Ȃ��A���o���ł��BCrusaders��E.W.&F.�Ȃǂ̃T�|�[�g�E�����o�[�Ƃ��ėL����R.Bautista���Q�X�g�Q�����Ă���ȊO��Bobo�̋��m�̃u���W���̃����o�[�Ōł߂��Ă���A�ςɃX���Ă��Ȃ������ň�r�ȃ��e���E�T�E���h���y���߂܂��B �@���W���[�E�����[�X�ł̃Z�[���X���ӎ����Ă�Dave Grusin�̋Ȃ�A���ꂵ���ł͂�����������Ă��Ȃ�(��)�W�m�E���@�l���̋Ȃ����グ��ȂǁA��S�̑I�Ȃ̐Ղ�������B�I�[�v�j���O�ŕ�����o�`���̒������~�W����M�^�[�E�J�b�e�B���O���ō��I�B���e���E�p�[�J�b�V�����ƃz�[���E�Z�N�V�����A���ʂȃp�[�J�b�V�����E�v���C...���̋Ȃ���Ԃ̂��E�߂ł��B��̐����������Ă���悤�ȃA���o���ł��B |
 �������` /Seychelles (1976�N) ���I�[�v�j���O�̃A�R�[�X�e�B�b�N�E�M�^�[���炢���Ȃ胊�]�[�g���o�ɐZ���A�����̃\���E�f�r���[�ՁB�T�f�B�X�e�B�b�N�E�~�J�E�o���h�A�T�f�B�X�e�B�b�N�X�Ȃǂ̊������o�āA���{�̃N���X�I�[���@�[/�t���[�W�������\����M�^���X�g�Ƃ��đ劈�A�V�ѐS���ڂ̃T�E���h�͍��ł��t�@���͑����͂��ł��B�ǂ������{�̉Ă�������������ʂ���������T�E���h�E���C�N�́A�Ƃ����m�y�ɂ��Ԃꂪ���ȓ��{�̃~���[�W�V�������������ɂ����čD�������Ă܂��B���E�߂͇@<Oh! Tengo Suerte>�Ɩ��ȇC<����̃Z�C�V�F������>�B�g���s�J���ȕ��͋C��t�̑O���ƃ��b�N�E�`���[���Ō��������܂�㔼�̃o�����X���▭�ł��B �@�ŋ߁A�t���Ƃ������������Ň@�̃p�N���̌��l�^���I�B���܂�̃N���\�c�U��Ɏv�킸�������Ă��܂��܂����B��������D���ŗǂ������Ă����Ȃ������̂ł����A�܂������l�^��70�N��̑�䏊�u���e�b�V���E���b�N�E�o���h�̋Ȃ������Ƃ�...�A�S�R���т�����20�N�ȏ�C�t�����ɂ��܂����Ƃ��B������ɂ���(?)�A���m�Ԃ����Ă�����Έ������肾���Ă���A���o���ł��邱�Ƃɂ͊ԈႢ�Ȃ��悤�ł��B |
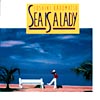 �p���q�� /She is A Lady (1987�N) ���ނ̉��y���̒��ɁA�̃��m�ȊO�ւ̎w�����̓f�r���[��������m���ɑ��݂��Ă����Ǝv���B������w�Ŏ����ނƉ߂��������N�Ԃł݂��ނ̉��y���̒��ɁA�B�Y�Ȃǂ̃V�e�B�E�|�b�v�X���o�ȊO��Luther��R&B�Ȃǂ̃\�E��...�_���X�E�~���[�W�b�N�ւ̓���ƂƂ��ɁA�ނ�����̃N���X�E�I�[���@�[�E�T�E���h�X�|���Ă������Ƃ͊ԈႢ�̖����������B�s����������܂܂̃f�r���[���N�ԁB�������ڐЌ�ɂ悤�₭���������̍�i�ւ̔������̒��ŁA���̃A���o���̂悤�ȃC���X�g�E�A���o���������悷�邱�Ƃ����R�̗��ꂾ�������A����Ӗ��ł̓v���Ƃ��ĉ��y����Ă����ȏ�A��x�͂���Ă݂����������Ƃ�����������т̏u�Ԃł����������Ƃ��낤�B �@����ȃA���o�����畷�����Ă���T�E���h�́A�i���p�Ȋp���̃C���[�W�ɂ҂�����́A�����������ۂ��Ƃ���͂�����̂̏��̎q�̋C���������߂Ȃ�j���Ȃ������ăT�[�t�B�������Ⴄ�ʂ̋C�������������Ă������̂ɂȂ��Ă��܂�(????)�B����A�f���Ɋi�D�ǂ��ł��B����I�ɓ��{�̃t���[�W�����E���������Ă������������ɁA���ɋM�d�ȃC���X�g�E�A���o���Ƃ��Đ����ƕ������܂��Ă��������܂�����B���ƁA���̃A���o���������[�X���ꂽ���̃c�A�[�ŌĂ�ł��ꂽJerry Hey��Larry Williams�̃��C�u�E�p�t�H�[�}���X�����ꂽ����...���ӂ��Ă���܂��B |
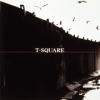 T-SQUARE / S.t. (2000�N) ��T-Square�Ō�̃A���o���B����A���ł��X�N�G�A���Ă����Ȃ���...�m���܂��������ǁA���̃X�N�G�A�͂�������l�̃��j�b�g�ŁA�o���h�Ƃ��Ă͍Ō���Č������ق�������������...�B �@80�N�ォ����{�̃t���[�W�����E�V�[���Ɋm�ł���n�ʂ�z���Ă�������o���h���A���I���܂����Ō�̍Ō�ɒH������̂́A���Ɍy�₩�ł��Ȃ₩�ŁA����ł��ăG���[�V���i���Ȕ��Q�̃t���[�W�����E�T�E���h�������Ǝv���܂��B���X�̃����o�[�̕ϑJ���o���������̂́A���̃o���h�̖ڎw���Ă����S���͕ς�炸�ɂ��Ă����Ǝv���܂��B���̃A���o���Ɏ��߂��Ă���<Man On The Moon>���Ă���ƁA���̃o���h����̂����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��^��ň�t�ł��B���̋Ȃ͂���ȋG�߂ɕ����ɂ͂߂��Ⴍ����ǂ��ł���B����<ca et la>���A�����ƕ]������ėǂ��Ȃ��Ǝv���܂��B���e���E�t���C�o�[�Ɉ���<ALE-LEYAH-YAH>�Ȃǂ��v���U��Ƀh���C�u���Ȃ��畷�������ȂƂ��Ď��̂��C�ɓ����1�Ȃł�����ɂ͉Ă̗[��ꎞ�ɂ��Е�������<An Evening Glow>�ȂǁA�{���ɗ��̑������f�G�ȃA���o�����Ǝv���܂��B |
��T-SQUARE�̔ߌ� �@���̃o���h�͖{���ɐ��X�̃����o�[�ϑJ���o�����Ă��܂��B�f�r���[�����̃`�F���W�͂Ƃ������Ƃ��Ă��A�M�^�[�̈������������[�_�[�Ƃ��ē������t�����g�̃T�b�N�X�̈ɓ��^�P�V�Ƃ̂Q���ŔŃo���h�͗L���ɂȂ��Ă����܂����B�h�����ɑ����A�x�[�X�ɐ{���Ƃ������̒��e�N�E�����o�[������胁���o�[�̎������肵�Ă������ɁA�����ɏ���Ĉɓ��^�P�V�̓o���h������܂����B����Ӗ��ł͈ɓ��̃��K�}�}�Ǝ��̖ڂɂ͎ʂ��Ă��܂�������...�B����ɉ��������̂��{�c��l�B�ނ̍Ő�[�̊������A�X�N�G�A�s���̂e1�̃e�[�}�ȂƂ�������ł��傤�B������������˂�����ŁA���������̂��܂�ɐ낪�����Ȓ��ɂ��Ă����Ȃ������̂������l�I�ȂȊ��z�ł��B �@�����Ė{�c���̒E�ތ�ɁA�V���ȃ����o�[�����R�̂悤�ɕ�[����A����Ӗ��ł͌��_��A�̃����f�B�A�X�ȃT�E���h�ɖ߂�������ނ�ɑ��āA�ǂ��������Ƃ��A�ꕔ�t�@�����җ�ɔ��������̂ł��B�X�N�G�A�֘A�̃z�[���y�[�W�̂a�a�r�ŁA��ςȑ����ɂȂ��Ă��܂����炵���ł��B�����ł̖ڂɗ]����Ƃ�Ƀ����o�[�{�l���{��̏������݂������߁A���Ԃ͑�ςȍ�����ԂɊׂ��������ł��B����Ȏ��Ԃ��d���݂��v���_�N�V�������A�������������������o�[�S���̉��قɂӂ݂���A�������ɓ��̃��j�b�g�Ƃ��ăX�N�G�A�����Z�b�g���Ă��܂����̂ł��B���{���ւ�l�C�t���[�W�����E�O���[�v���������U�Ɏ������Ƃ����킯�ł��B �@�͂����茾���Ă��̃o���h�̃T�E���h�R���Z�v�g�����߂Ă���̂̓v���f���[�T�[�ł���B����������o�[�l�ɑ��Ĕ����W��������Ȃ�āA�������N�����t�@���͈�̉��l�̂���Ȃ̂ł��傤�B�����o�[������e�C�X�g�������ē��R�B�C�ɓ���Ȃ���Ε����Ȃ���ǂ��̂ɁA�����]���ĐV�����o�[�����Ȃ��...�B����A���Ȃ����č\��Ȃ�����ǁA����ȑ������܂ŋN�����A���̃t�@���B�̍߂͏d���ł���B �@���������Ēm�荇�����x�[�X�̐{������A�V�����̃T�b�N�X�̋{�肳��A��������{���ɐl�Ԗ�����f�G�ȕ��ł��B����ȑ����̐����������āu���E�v�ɂȂ�����������Ă��Ƃł�(^^;;)�B �@���݂̃X�N�G�A�́A���ق����͂��̑���������������o�[�����Ń��C�u�Ȃǂ��s���Ă��܂��B�܂��{�c���Ȃǂ������āuwith Friends�v�݂����ȃA���o�������삵���肵�Ă��܂��B���r���[�����܂���A����Ȋ����`�Ԃ́B�t�@���ƃ~���[�W�V�����A�v���_�N�V�����ƃ~���[�W�V�����̊W�ȂǁA�l���������邱�Ƃ̑����G�s�\�[�h�������Ǝv���܂��B�ł��ˁA����Ȏ��Ԃ��N���������Ƃ́A�ǂ��̉��y�G���ł��Љ��Ȃ������ł���ˁB�������ĕ����`��Œm�蓾�����ƂȂ̂ŁA100%���m���ƌ�����Ɗm�͂���܂���B�������炸�Ƃ������炸���ĂƂ��낾�Ǝv���܂��B����ȑ����ɂȂ��������Ƀ����[�X���ꂽ�A���o���̏o�����A���܂�ɗǂ����������Ɏc�O�łȂ�܂���B |